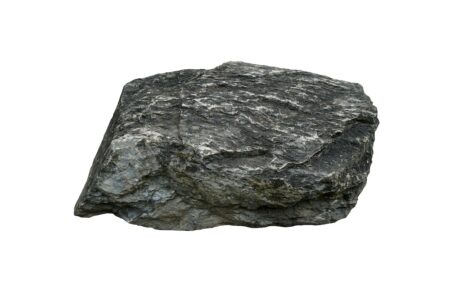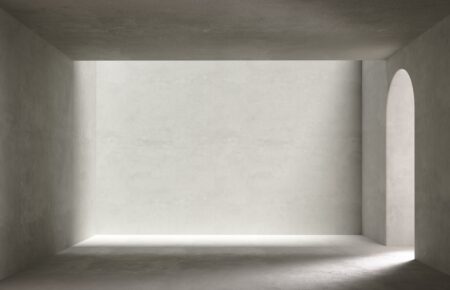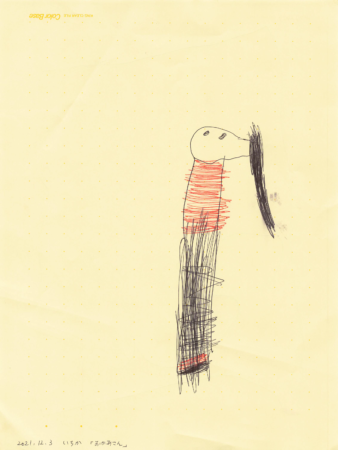それは
人を信用するかどうかの判断材料に小説が使われるとは。
どんな本だ?2000年代初頭のVillage Vangard(ヴィレヴァン)。俺は絶対に読まなくてはいけない。
公式に発表されているあらすじは、以下。
『人類がはじめて月を歩いた夏だった。父を知らず、母とも死別した僕は、唯一の血縁だった伯父を失う。彼は僕と世界を結ぶ絆だった。僕は絶望のあまり、人生を放棄しはじめた。やがて生活費も尽き、餓死寸前のところを友人に救われた。体力が回復すると、僕は奇妙な仕事を見つけた。その依頼を遂行するうちに、偶然にも僕は自らの家系の謎にたどりついた……。深い余韻が胸に残る絶品の青春小説。』(新潮社ホームページより)
主人公はかなりハードな環境にありながらも、物語全体に暗さはなく、絶望や孤独の中にこそある美しさ、というか
そういう環境に身を置くことで感じるある種の陶酔感が生々しく感じられる物語。限りなく『青春小説』。
初めて読み終えた後、「ああ、だからビレバンのポップに、『これを読まずに大人になったやつを俺は信用しない。』って書いてあったんだな。」と思った。
僕自身、たまたまその1年後にオーストラリアへ住むことになったけど、この小説が自分の根底で強さを保ってくれていたことは間違いない。と思っている。
『』
さて、ムーンパレスというゲストハウスがNYに実在していたらしい。経営者は日本人だったということ。残念ながら今はなく、2016年末に閉業したそうだ。
これはきっともしかすると、この本の熱心なファンだったのだろうか。
失い続けた先に、何があるのだろう。孤独で、もやもやした青春――。名手オースターの人気No.1作品。
Text : 小佐直寛(Naohiro Kosa)



の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)