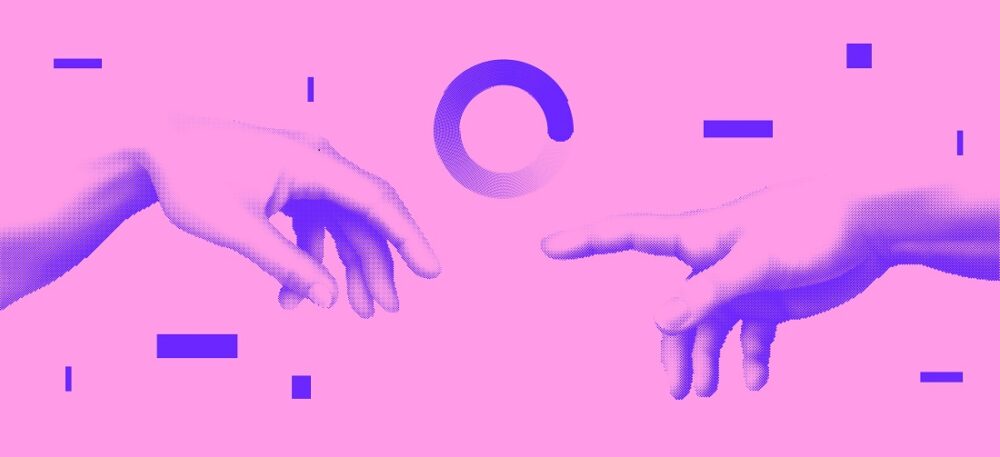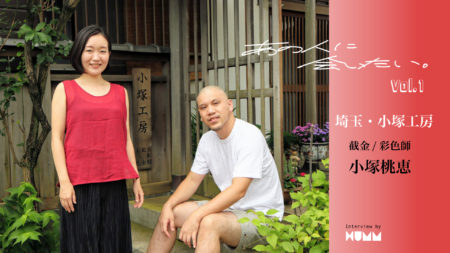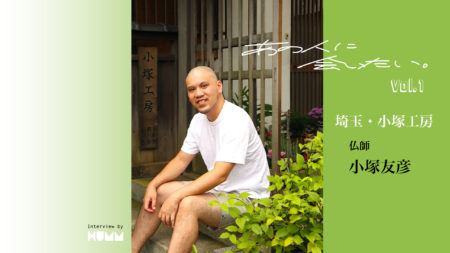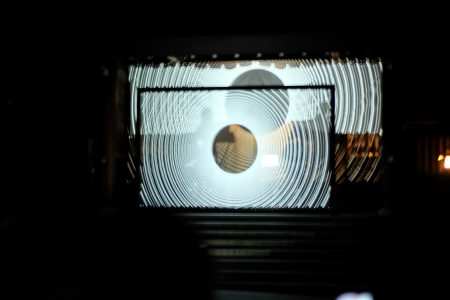仕事・子育てに全力投球で、音楽を作るための精神的体力がつくれず、活動できていないことそれ自体がストレスに。人に話せば愚痴にもなりそうで、どこかで蓋をしてきたこの悩み。このままでは良くないと考えた末に、「京都 芸術 支援」と検索して、KACCO(京都市文化芸術総合相談窓口)と、KYOTOHOOP(きょうとふーぷ・京都府地域文化創造促進事業)の存在を知ることになります。文化芸術も、「子育て」「介護」「就職」などと同じように、支援を受けていいんだ、そう感じられました。KACCOのご担当者と面談をする機会を得られ、さまざま色々なことをお話しできました。そのなかで話題に出たのが「アートマネージャー」という役割。お話に聞くまで恥ずかしながら、僕は知りませんでした。そんな役割の人がいらっしゃったんですね。
アートマネージャーとは
アートマネージャーとは、文化芸術と社会を繋ぐための仕事をする人のことを言うそうです。
ざっと調べてみると、その仕事は多岐に渡り、企画・展示会の準備・事務作業・スケジュール調整・資金調達などなどなど…。およそアートに関わるマネジメント業務全般を言います。僕たちが普段、ビジネスで行っている実務を「アートの分野」で行う人のこと、と僕は捉えました。世の中にそのような仕事をしている人がいたのか!という発見でした。
(文化芸術の活動について相談できる場所があるという安心感)
文化芸術関係者はノンエッセンシャル・ワーカー(non-essential worker:人々の日常生活の維持に必須ではない仕事に従事する労働者)であり、当事者もまたそれを理解していると思います。だからこそ、だれにも相談できない・相談をしようとしない(そもそも相談するという発想がない)ことが常態化しているのではないかと私は感じています。一人では悩みが深まってしまうことも、話しをすることで気持ちも楽になるでしょう。それも、おなじ当事者同士であれば会話の内容に気を遣う必要もありません。
この記事の中ではすでに触れましたが、京都市には、KACCO(京都市文化芸術総合相談窓口)という団体があり、話を聞いてくれます。文化芸術は、それに取り組む期間が長期間にわたります。様々なライフイベントがある中のことなので、平らな道ばかりでないことは容易に想像できます。コロナ禍以降、生活様式も住む場所も多様性が生まれました。芸術活動は都市部だけで行われているわけではありません。その点で、どのような地域でも、文化芸術関係者のための相談ができる場所つくり(他機関との連携含む)に取組むことは重要なことです。そうした土壌を作っていくことが支援となり、文化芸術関係者の孤立を防止し、ひいては豊かな文化芸術の創出にも繋がるのではないかと思いました。
(楽しんで行動範囲を広げて、気が付けば価値の創出に繋がっているといい)
京都府に地域アートマネージャーが設置されたのは2022年度とのことです。立ち上げの際に就任されたアートマネージャーはどのようなことを考え、取り組みを実施されたのでしょう。きっとたくさんの試行錯誤されたのだろうと想像します。京都府で募集されている地域アートマネージャーは有期雇用(会計年度任用職員)です。数年単位で人が交代する可能性を考えると、人が変わっても継続して引き継げるテーマのようなものがあると良いのかもしれません。これから先を見据えたときにテーマは必要だと思います。
いつの時代でも、社会と芸術は互いに影響しあっています。表現活動もその蓄積の上に成り立っています。文化芸術はノンエッセンシャルワークではありますが、社会には、やはり文化・芸術が必要であると感じます。府にアートマネージャーが設置された背景には、社会での文化芸術のあり方を模索しようという姿勢が汲み取れます。国と地域が協力・分担し、文化芸術の取り組みを市民一人ひとりの身近なことにできるように、僕もできることを考え、実行しようと思います。
ここまで読んでいただきありがとうございました。