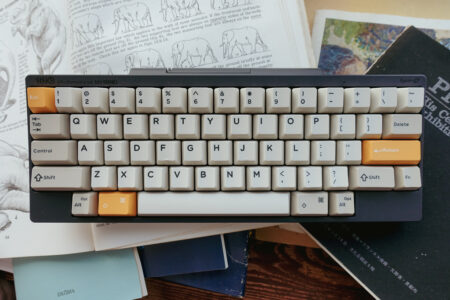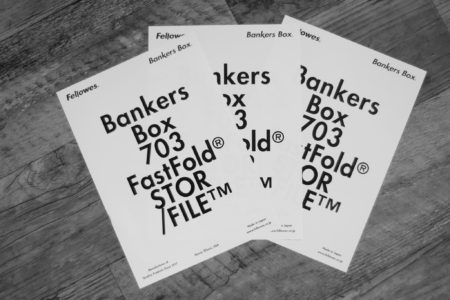制作(音楽を作ること)はおもうようにいかない。僕にとって、曲を作るということは結局のところ、音への反応・条件反射のようなもの。そのため、なかなかジャンルも定まらない。ローファイヒップホップが作りたくても、出来たものはテックハウスみたいになったり、アンビエントになったり、と。理想とは違っても、出てきたものが、今の自分にできる音楽。そういう意味でも、どうやらやっぱり音楽は偽らない。鏡のようなものだ。自分に対して寛容になろう。違う違う‥こんなんではない!では、一歩も前に進めないもの。
音楽を作るのだ、というパートが、僕には不可欠だ。それは、食べること、寝ること、と同じように普段の生活のなかで行うことに、意味があると信じている。
いきなりで何だけども、僕には、音楽のことを共に追求する「友達」がいない。それは、コミュニティに属していないから、というのが一つの理由なのかもしれない。
だから友達が欲しいと思う。
理想のコミュニティ像はある。それは、とても「フラットな」集団だ。ビギナーもプロフェッショナルも、感覚的な「垣根」のない、そういう場所だ。けれど、コミュニティの見つけ方も分からないまま、30代に入ってしまった。(理由の一つには、自分が田舎でローカルな場所に住んでいるからかもしれない。)
どうにかならないものか。
コミュニティに求める大切なもののひとつは、他人の目(耳)だ。ただ、客観的に、だけでなく、共に進んでいくための、他人。それは、お互いにアドバイスできる人間関係。情報を共有できる相手。音楽のフォーラムを探してみようか…でも、リアルに勝るものはないよね。直接話してる方が、断然いい。
ひとと、雑談していると思いがけずアイデアが湧いてきた、ということには経験がある。相手の言った話に「それ、めっちゃいいね!」と共感し、それがアイデアのきっかけとなる。あれかこれか、どうするどうする、で悩んでいたことが、パーっと道筋が見えることがある。
そういうコミュニティに属したい。もっというならコミュニティを作りたいです。もっといろんな人と話しをしたい。何してるの?ちょいと語ろうよ。くらい、気楽に。
2013年ごろまでは、わりに精力的に活動していた僕の音楽名義 “nil.team nest” のアイコンは、テント⛺️にしているんだけど、それはいろんな人とアイデアが集まる場所になれば。という考えから始まったものだった。
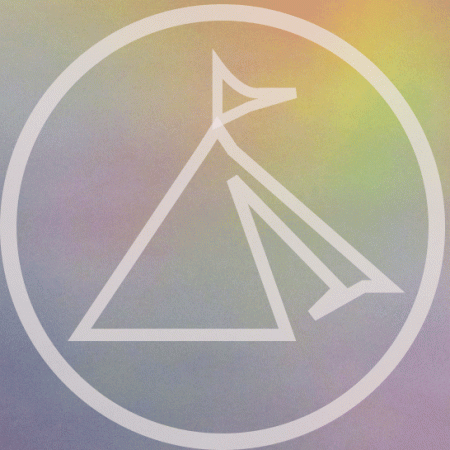
nil.team nest というユニット名の由来も、平たく言うと、”ひとりじゃ、価値のあることは出来ないけど、チームになれば居心地の良い場所ができるかもね”という思いだった。実際はソロでの活動だったけども。活動のなかで楽しかったのは、ライブでドラム奏者に参加してもらったり、CDのデザインをデザイナーと一緒につくったこと。どちらも、じぶん1人ではない、チームでの仕事ですよね。
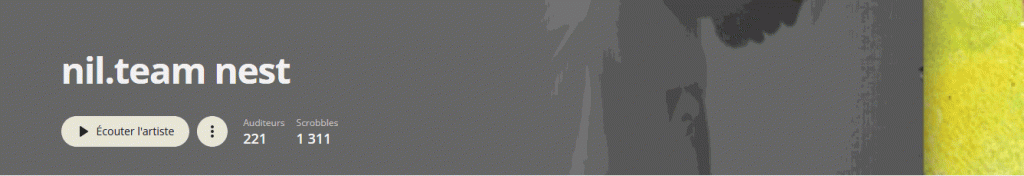
今年2020年の目標は、そういうつながりが見つかるように、TwitterやInstagramに積極的に投稿したい。繋がってもいいよ、という人は是非よろしくお願いします。
あなたのつくるものが音楽でなくてもいいし、とくに何もしていなくても全然問題はありません。インターネットならではの、気軽に意見を言ってくれたり、口出しをしてくれる人、フォローしあいませんか。
X(Twitter) @___KOSA
Instagram @_humm_kosa
Bandcamp nilteamnest.bandcamp.com
制作を続ける生活をしていると、どういうわけか悩みばかりになる。
制作物(作品)というのは、ほんとうに偽らない。自分を写す鏡で、それはときどきひどく醜いし、ときどきハッとするような美しいものが生まれることもある。 自分の探究に他ならない。
理想があり、表現したい感情があり、日々があり、さらに言うなら人は皆んな、いつか死ぬという期限がある。人並みに子供もいるし、仕事もしてる。みんな大切。あれもこれも大事。
思うようにはいかないさ。それでも、音楽が好きだという事実も、表現したいという気持ちも変わらないんだもんな。
たとえ傑作が出来ても、よし、これでもう作らない!という満足はしないような気がする。だから、瞬間的にでも、「お、良いんじゃない?」と思える瞬間を増やしたい。
多少、ヘンでもいいじゃない。多少、不完全でもいいじゃないか。
たぶん、同じような悩みを持ってる人は多いと思うんだ。
このHUMM.ブログもどうなるかわからないまま始めたけど、丸二年たった今は、毎日150人を超える人が訪問してくれている。(やってみなけりゃ分からない)
制作物も、もっとさらけ出してみよう。バッシングや、冷評、無視にも恐れることなく。出さないと、無いのと同じ、だからね。
Kosa Naohiro の最新音楽は、Soundcloud,または Instagramにアップロードしていきます。
Soundcloud: https://m.soundcloud.com/kosanaohiro
Instagram: https://www.instagram.com/_humm_kosa/

手帳は、ほぼ日手帳を使っています。仕事のために、ちょっと先の予定を確認しようとした時に、2月26日のよみものが良かったので下記に引用します。
「やりたいこと」というきらめく言葉に人はとらわれがちだけど、
ほぼにち手帳 2020 - 2月26日(水)
「できること」を増やさないと、やりたいことも皮相なまま育っていかない。
できることを増やすには、「やるべきこと」をやる、地道な積み重ねが大事。
いまやるべきことを高い質で心をこめてやり通すことで、思いがけずできることが増え、人が歓んだり、新たな能力が見出されたりし、「あ、やりたいことがやれてる」と気づく。
____山田ズーニーさんが『大人の小論文教室。』の中で
Text : 小佐直寛(Naohiro Kosa)