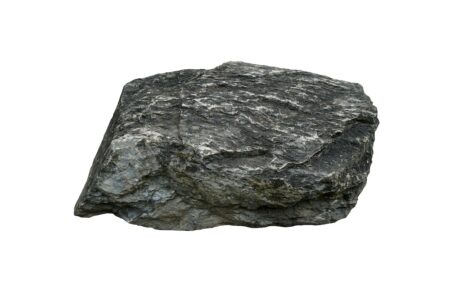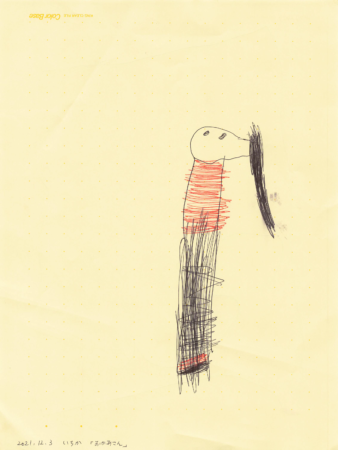世の中に「やったほうがいいこと」はたくさんあります。それは仕事のうえでもそうだし、子育てや教育のうえでも、また健康についてもきっとそうです。そういう、やったほうが良さそうなこと(情報)は自分から探しに行かなくても知ってしまう(目に入ってしまう)ことが大半ですよね。インターネットをひらけば、AIの提案、広告掲示や関連記事で過剰なほどたくさんの情報を目にしていますから。「ほ〜、そうなんだ」と思ったり「いや、これは嘘っぽいな」と判断しますよね。毎日そんなことに曝されているのですから、そりゃあ誰だって疲弊しちゃいますよ。
やらないことを決める
仕事や習慣、自分を取りまく環境を変化させたい。そんなふうに考えますよね。そのために、昨日までとは違うなにかを始めようと考える。そのときに重要な要素は、「時間」です。何かをするためには、何かをやめる・減らす必要がある。
会社員をしていると人事をはじめとして様々な命令を受けることになります。資格の取得もそのうちの一つです。資格を持っていると給与に手当がついたり、役職を上げるための必須条件であったりもします。どうやら、部下に資格を取らせることも上司の仕事のようですから、忘れたころに必ず資格取得の打診(強要)を受けます。一見、こちらに選択権があるような言い方ですがその実そんなことないところがミソです。自分のキャリアについていつも考えておくと急な打診にもわずかながらも心の余裕が持てます。降格やクビにならないのであれば辞退することだって選択肢の一つです。手に入れたい結果が出世のためだったり、進学のためだったりと良い成績を残すことを目標にするならば、きっとありとあらゆる手段を講じることは有効でしょう。そうすべきです。しかし、そうではなく(自分の意思よりも)相手の顔色をうかがったり、流れできめてしまうことはちょっとストップ。本当にそれでいいの?と自問したい。
やらないことを決める。とても大切なことです。僕にとって大事なことは二つ。①子どもを育てる家庭 を守ること、と②じぶんの仕事をつくることです。そのために必要な量があればいい。言ってみればそれ以外は優先順位が低いと言えます。
教育でもそうだろうと思います。学びたいことのための大学であり、資格制度です。日本に幾つの大学と国家資格があるか、調べてみました。大学が815校(国立86、公立103、私立626)、国家資格が293です。どこの大学へ行ったっていいんです。どこにでもきっと、自分に刺激をくれる人、研究に没頭できる環境、向き合うための贅沢な時間がきっとあります。他人と比べる必要も、ましてや盲目的に合格を目指すこと(資格取得を目標とすること)に躍起になる必要などない。やったほういいと言われることを漏れなく行うことなど、無理です。自分が必要とおもうことをすれば良い。
人生、というと膨大な時間に感じますが、一日24時間でさえこんなに短いのです。他人より損をするのではないかと不安に考えるより、この一週間をどう過ごすかを考えてみませんか。そのほうがきっと豊かだと思います。

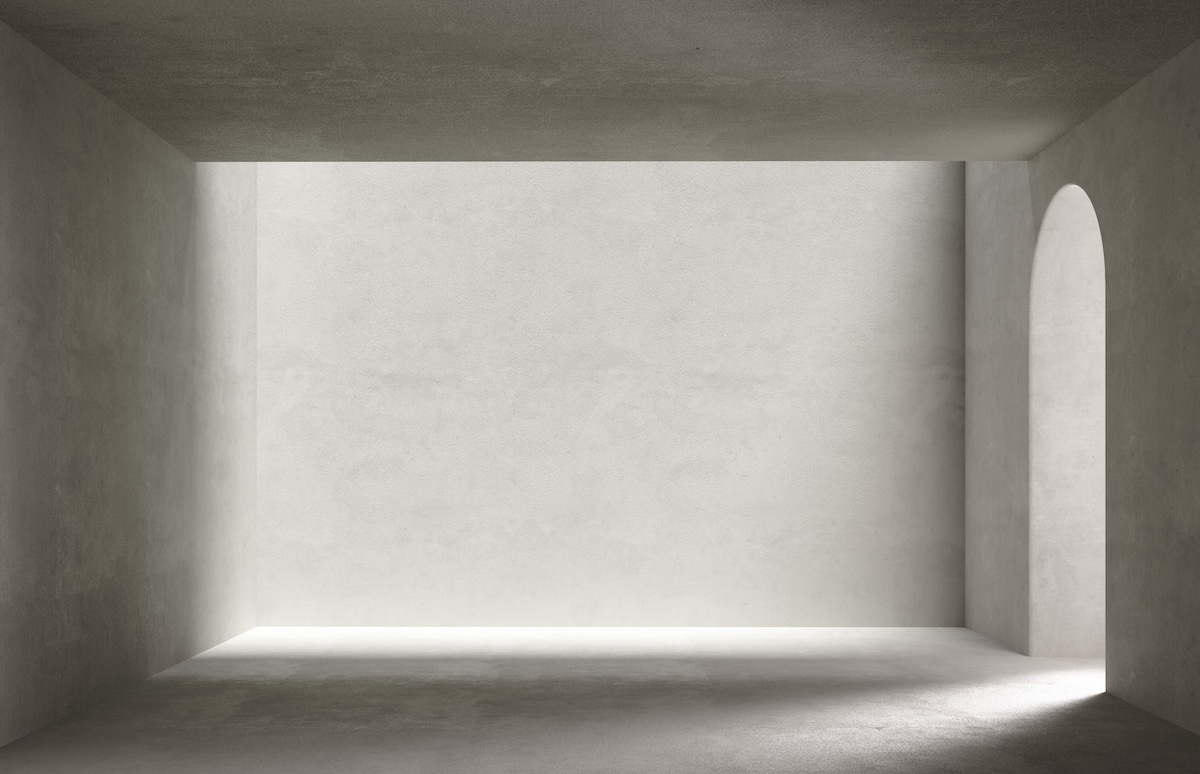

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)