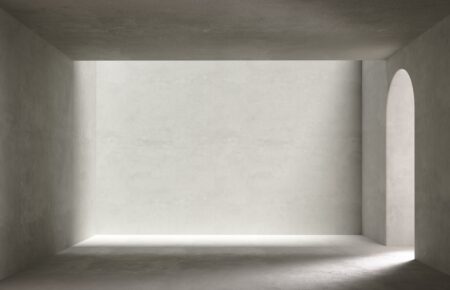[itemlink post_id=”4648″]
ずいぶんと久しぶりに、オースター作品を読んだ。
この本の前に読んだのは、「幻影の書」だった。今作も、オースターが得意とする「物語内物語」が読者を緩やかにスムースに思考の海へと導いていく。すでに深いところまで来ていた、と気づいた時には、複雑に絡み合った物語の潮に身を任せている自分に気がつく。ふと、
本から目を離し、何ページまで読んだっけ?と確認すると、そんなにページは進んでいない。それにしても、ずいぶんと遠いところまで来たなあと思わされる。オースターの作品は現実的である。現実的な物語でありながら、ありもしないようなことを信じさせられる力がある。もしかして僕たちの日常にも、これだけも起伏に富んだ出来事の可能性があるのかしら、と思わされる。
主人公は、自分をできるだけ冷静に見つめようとしている。自分と、適切な距離を取ろうとしている。自分をコントロールできると思って、少なくとも、そうしようとしている。考えがまとまらないうちから、出来事に反応し、世界と向き合おうとしている。
緻密な描写で描かれるニューヨークの街、手に取るように伝わってくる主人公の心理描写。浮かんでは消えていく思考は、(ごく日常的に)誰の頭の中にもあるものだろう。柴田元幸氏による本訳の、流れるような言葉のジャブに身を任せていると、まだ、物語が終わって欲しくない、とページをくりたくない衝動に駆られる。
物語の最後は、大どんでん返しも、衝撃のラストも用意されていない。しかし、オースターらしい優しさ、愛情に包まれたまま物語は終わる。屈指のストーリーテラーによる静謐な室内楽。深い余韻を保ちつつ、思考の海から上がってくる自分に気づく。
Text : 小佐直寛(Naohiro Kosa)


の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)