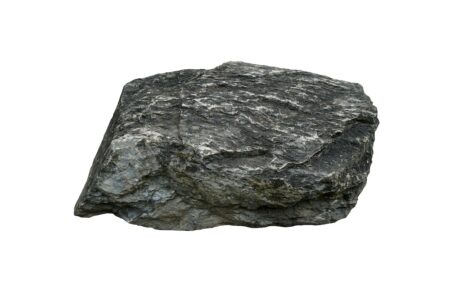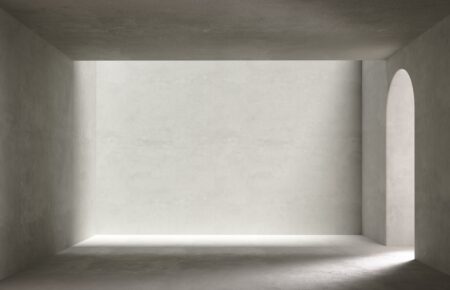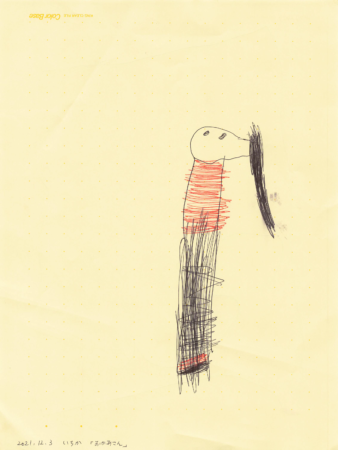Smashing Pumpkins(スマッシング・パンプキンス)と聞いて、反応をしたあなたは多分、ぼくと同年代か、少し上の世代の人じゃないだろうか。シカゴで結成されたスマパンは、2000年の一次解散までに、5枚のスタジオ・アルバムを発表している。
1991年「ギッシュ」
1993年「サイアミーズ・ドリーム」
1995年「メロンコリーそして終わりのない悲しみ」
1998年「アドア」
2000年「マシーナ/ザ・マシーンズ・オブ・ゴッド」
メンバーチェンジを経て再結成後の主なスタジオ・アルバム
2007年「ツァイストガイスト」
2012年「オセアニア〜海洋の彼方」
2014年「モニュメンツ・トゥ・アン・エレジー」
2018年「シャイニー・アンド・オー・ソー・ブライト VOL.1」
(18年ぶりに、ビリー・コーガン、ジェームス・イハ、ジミー・チェンバレンのほぼオリジナル・メンバー)
1991年、デビューは「ギッシュ」だったが、思うようにセールスが伸びず、ビリー・コーガンは、次のアルバム「サイアミーズ・ドリーム」が成功しなければ、その次はないと考えていた。そのプレッシャーの中、「1979」「Today」を収録した同アルバムは商業的にも成功を収め、バンドは軌道に乗った(この時、ビリー26歳、イハ25歳)。その「サイアミーズ・ドリーム」も、もちろん好きなのだが、ぼくとしては抜群に推したいのが「メロンコリーそして終わりのない悲しみ」。このアルバムは、本当にすごい。
途方もなく激しくて、美しくて、切ない。螺旋状にグイグイ引っ張られて、大げさではなく、油断していると、ちょっと涙が出てしまう。全米だけで、500万枚という途方もない枚数を売り上げた前作のアルバム「サイアミーズ・ドリーム」を発表した後、手にした成功にとらわれることも、惑わされることもなく、躊躇することすらなくバンドとして進んだ結果、見つけたテクスチャー。決別と前進する勇気が姿勢として詰まっている傑作アルバムだ。アルバムのレコーディングに入る直前に、ビリーはこう言ったという。
「『サイアミーズ・ドリーム』は、今でも良いアルバムだと思ってる。僕は、もう1枚、みんなの頭をブッ飛ばすような、とんでもなく凄いアルバムを、どうしても作りたいんだ。」
そして、スマッシング・パンプキンスは、「メロンコリーそして終わりのない悲しみ」で、本当にそういう傑作を作り上げてしまった。
[itemlink post_id=”4735″]
このアルバム2枚組にするというアイデアは、94年2月の再来日の時点で、ビリーの頭の中にはあったようだ。それぞれが違う雰囲気を持つ2枚のCD。そのことをビリーが構想した通り、Disc1(赤色)の”dawn to dusk”は、エネルギッシュな激しい音楽。Disc2(青色)の”twilight to starlight”は静かで美しい音楽、という構成になっている。と言いたいが、実際は、Disc1にもDisc2にも一枚の中に激しい曲もあれば、次は静かで美しい曲、と言った風に、それはとてもバランス良く配置されている。そして、Disc1もDisc2もそれぞれに完結しており、一枚の中にストーリーがある。
何れにしても、90年代に二枚組のコンセプト・アルバムを作る。という発想が凄いじゃないか。
最終的に、アルバムのために作られた曲数は54曲にまで膨れ上がり、そこから収録の28曲にまで絞られた。時間にして、122分と言う 圧倒的なスケール、限りなく美しい音楽。胸を掻きむしりたくなるほどインスピレーションに満ちていて、とてもスピリチュアルな大傑作アルバム。このアルバムを聴けば、どこかに置いてきてしまった自分を、取り戻せるような気がするんです。
それくらい、僕らにとっては、人生のマスターピースなアルバム。
「メロンコリー‥」の中でも一、二を争うくらい好きな曲。それのライブ版. “Here Is No Why FROM” from “Mellon Collie and the Infinite Sadness”

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)